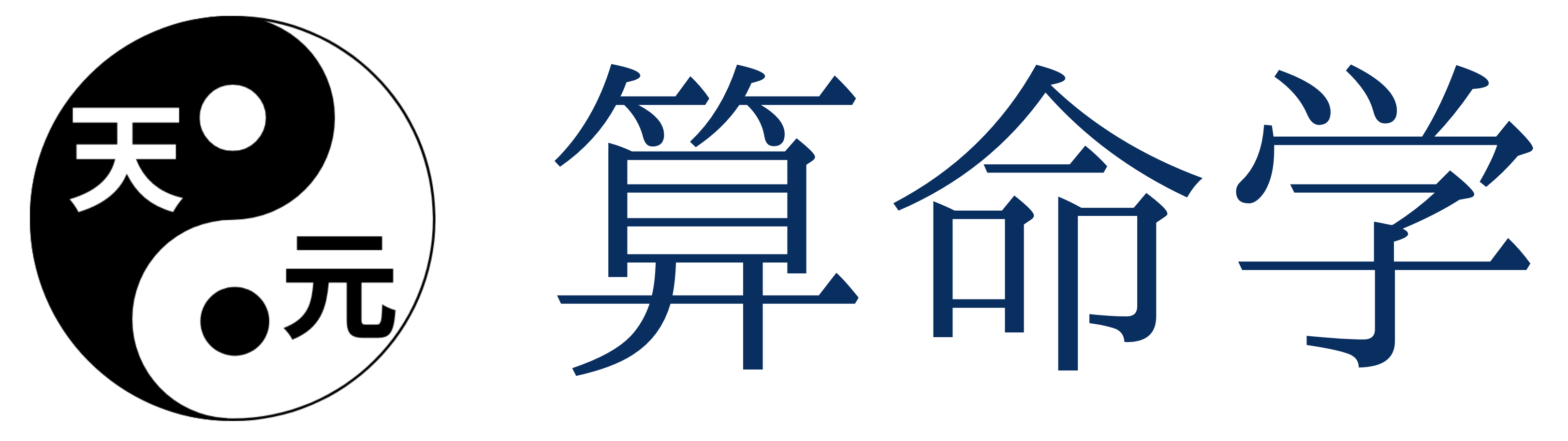こんにちは。南極老人です。 多くの人が、商売繁盛や豊かな実りを願って、お稲荷さんを訪れます。しかし、熱心にお参りしているのに、なぜか人生が好転しない、むしろ苦しいままだと感じる方はいらっしゃいませんか。
それは、お参りの仕方が間違っているから、という単純な話ではありません。 もしかすると、ご自身の「心の在り方」が、お稲荷さんが司る「豊かさの流れ」と逆行してしまっているのかもしれません。
今日は、古くから「お稲荷さんに嫌われる」とされる人の特徴を5つ、ご紹介します。 これは迷信や脅しではなく、実は、心理学や脳科学の観点からも「幸福や成功から遠ざかる人の特徴」と見事に一致するのです。
なぜそうなるのか? その「なぜ」を深く掘り下げながら、私の師である天元先生の教えも交えて、あなたが本来持つ運の流れを取り戻すヒントをお伝えします。
「お稲荷さん」とは、私たちの心の鏡
本題に入る前に、一つだけ。 お稲荷さん、すなわち宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)は、稲=お米、つまり「食」と「命」そのものを司る神様です。そこから派生して、商売繁栄や五穀豊穣の神様として親しまれています。
「嫌われる」と聞くと怖く感じるかもしれませんが、神様が人間のように感情的に誰かを「嫌う」わけではありません。 ここでいう「嫌われる」とは、「その人の在り方が、お稲荷さんが象徴する『豊かさのエネルギー循環』にうまく乗れない状態」と解釈してみてください。
豊かさとは、清らかな川の流れのようなものです。 せっかく豊かな水が流れ込んできても、受け取る器が汚れていたり、穴が空いていては溜まりません。 これからお話しする5つの特徴は、まさにその「器の穴」や「汚れ」のようなものなのです。
感謝を忘れ、「奪う」ことばかり考える人
最初にお伝えしたいのが、感謝の心を忘れ、「あれが欲しい」「これが足りない」と、常に「奪う(Take)」ことばかり考えている心の状態です。
一粒の籾(もみ)が、太陽の光、雨、豊かな大地という自然の「恵み」を受け取り、何十倍、何百倍ものお米となって実ります。 これは「受け取り(Receive)」と「与える(Give)」の循環そのものです。
「奪う」という意識は、この循環を根本から否定する行為です。 「足りない」という欠乏感(スカーシティ・マインドセット)に囚われていると、自分だけが得をしようと、他者や自然から奪うことしか考えられなくなります。 これは、豊かな実りをもたらす大地に、自ら塩をまくようなものです。
「当たり前」が幸福を遠ざける心理
心理学の世界に「快楽の順応(Hedonic Treadmill)」という言葉があります。 人はどんなに良いことが起きても、最初は幸福を感じますが、すぐにそれに慣れてしまい、幸福度が元のレベルに戻ってしまう現象です。
例えば、ずっと欲しかったブランドバッグを、ボーナスをはたいて手に入れたとします。 最初の数週間は、見るたびに心がときめき、幸福感に満たされるでしょう。
しかし、1ヶ月も経つと、そのバッグがあることが「当たり前」になります。そして今度は、SNSで友人が持っている新作のバッグを見て、「あれがないと私は満たされない」と感じ始めてしまうのです。
感謝を忘れるとは、まさにこの状態です。 今あるもの(健康、仕事、家族、食べ物)を「当たり前」だと感じた瞬間、私たちは「快楽のトレッドミル」の上を、延々と走り続けることになります。
「もっと良いものがなければ幸せではない」 「これだけでは足りない」
この「当たり前」の基準が上がれば上がるほど、幸福を感じるハードルも上がっていきます。 常に「足りない」と感じている心が、どうして豊かさを引き寄せられるでしょうか。 お稲荷さんがもたらす「ささやかな、しかし確実な恵み」に気づくことさえできなくなってしまうのです。
「奪う」姿勢が人間関係を壊す理由
ペンシルベニア大学の組織心理学者アダム・グラント氏は、人間を「ギバー(与える人)」「テイカー(奪う人)」「マッチャー(損得のバランスを取る人)」の3種類に分類しました。
研究によれば、「テイカー」は短期的には成功することがあっても、長期的には必ず失敗する傾向にあります。 なぜなら、周囲の人は「あの人は自分の利益しか考えていない」と気づき、次第に距離を置くようになるからです。信頼を失い、誰も協力してくれなくなったテイカーは、最終的に孤立します。
職場に、いつも「これ、手伝って」「お願い」と頼んでくるばかりで、こちらが困っているときには見て見ぬふりをする人はいませんか? 最初は「お互い様だから」と手伝っていた同僚たちも、次第に「あの人に関わると損をする」と感じ、距離を置き始めます。 結果として、その人は重要なプロジェクトのメンバーから外され、キャリアアップの機会を失ってしまうのです。
商売繁盛の神様であるお稲荷さんは、人との「ご縁」や「信用」がどれほど大切かを知っています。 「奪う」人とは、自ら「ご縁」や「信用」を切り捨てている人です。 そのような人が、真の豊かさである「人や社会との温かい繋がり」を築けるはずがありません。
天元先生の教え:「すべては借り物」という真理
これは、私がまだ天元先生に出会う前、自分一人の力で成功してやると息巻いて、見事に失敗し、打ちひしがれていた時のことです。
「南極老人よ」と、先生は静かに私に問いました。 「お主が今吸っている空気は、誰が作ったものかね? お主が歩いてきたその道は、お主が作ったのかね?」
私は言葉に詰まりました。 先生は続けました。 「我々が持つ才能、知識、経験、そしてこの命さえも、すべては先人たちや社会、自然からの一時的な『借り物』なのじゃ。我々のものは何一つない」
この言葉は、私の頭を殴られたような衝撃でした。 私は、自分の成功を自分の手柄だと信じ込み、「奪う」ことばかり考えていたのです。
先生は言いました。 「借り物であるならば、我々がなすべきことは一つじゃ。それを大切に使い、磨き、そして次の世代に『恩送り』として返していくこと。奪うのではなく、与える。これが宇宙の、そして商売の基本原理なのじゃ」
お稲荷さんが象徴する「実り」とは、まさにこの「恩送り」のサイクルです。 感謝とは、「今あるものが借り物である」と知り、その恵みに気づく心。 この心なくして、豊かさの循環は始まらないのです。
口先だけで行動が伴わない人
次に、お稲荷さんが力を貸しにくいのが、「あれをやりたい」「こうなりたい」と口では言うものの、実際の行動が全く伴っていない人です。
お稲荷さんは、農業や商売の神様です。 農業は、種をまき、水をやり、雑草を抜き、害虫と戦うという、日々の地道な「行動」の積み重ねです。 商売もまた、商品を企画し、作り、お客様に知らせ、届けるという「行動」なくして成り立ちません。
どれほど立派な願い(「大豊作になりますように」「お店が繁盛しますように」)を口にしても、畑を耕さず、店を開けなければ、結果はゼロです。 「口だけ」で行動しない姿は、稲の神様から見れば、「実りを得る意志がない」と宣言しているのと同じなのです。
自己不一致が自己肯定感を蝕む
心理学では、自分の言葉や信念と、実際の行動が食い違っている状態を「認知的不協和」と呼びます。
「資格を取ってキャリアアップしたい」(信念) 「でも、今日も疲れて勉強せず、動画サイトを見てしまった」(行動)
この矛盾を抱えると、人の心は強いストレスを感じます。 そして、このストレスを解消するために、私たちは無意識に2つの道を選びます。
一つは、行動を変えること(「よし、今から10分だけでも参考書を開こう」)。 もう一つは、信念を変えること(「どうせ私には無理だったんだ」「この資格は本当に必要だろうか」)。
多くの場合、行動を変えるよりも、信念を捻じ曲げて「やらない自分」を正当化する方が簡単です。 「口だけ」で行動しないことを繰り返すと、脳は「どうせ自分は口だけで実行できない人間だ」と学習してしまいます。 これが、自己肯定感が下がっていくメカニズムです。自分で自分を信じられなくなっている人の「願い」に、どれほどの力が宿るでしょうか。
行動しない心の奥にある「変化への抵抗」
私たちの脳は、現状を維持しようとする強力な機能(ホメオスタシス=恒常性)を持っています。 なぜなら、脳にとって「変化」はエネルギーを消耗する上に、未知の危険を伴う可能性があるからです。
「豊かになりたい」と願うのは、「変化したい」と願うことです。 しかし、行動しないということは、脳の「現状維持バイアス」に屈している状態です。 口(意識)では「変わりたい」と言いながら、本心(無意識)では「今のままの方が楽で安全だ」と、変化に強く抵抗しているのです。
ダイエットを決意したのに、無性に甘いものが食べたくなるのも、このホメオスタシスの仕業です。 あなたの意志が弱いわけではなく、脳が「いつもと違う!エネルギーが不足するぞ!」と危険信号を出しているのです。 お稲荷さんがもたらす「商売繁盛」や「豊穣」といった「変化」のエネルギーを受け取るには、こちらも「変化する覚悟」を行動で示す必要があります。
現実を動かす「小さな実践」の力
天元先生は、知識を教えるだけでなく、その「実践」を何よりも重視する方です。 先生はよく、膨大な論文や書籍から得た知見を、私たち弟子にわかりやすく教えてくださいます。
しかし、先生が必ず最後に言うのは、「で、今日から何をする?」という問いです。
「知識は、使わなければただの雑学じゃ。知っていることと、できることは全く違う。100の知識より、1の『小さな実践』こそが、現実を動かす唯一の力なのじゃ」
自己肯定感の低さや将来への不安に悩む人々(まさに、かつての私です)は、「大きな一歩」を踏み出せない自分を責めがちです。 しかし先生は、「大きな一歩は必要ない」と断言します。
「腕立て伏せが100回できなくても、1回ならできるじゃろ? 1時間勉強できなくても、1分間、本を開くことはできる。その『1』を笑ってはいけない。その『1』こそが、脳の現状維持バイアスという鉄壁を突破する、最も賢い一撃なのじゃ」
お稲荷さんへの祈りも同じです。 「大きな成功」をただ待つのではなく、「今日はこれをやり遂げます」という「小さな実践」を誓い、実行する。 その行動の積み重ねこそが、神様が応援したくなる「本気」の証なのです。
食べ物や命を粗末にする人
三つ目は、非常に根本的なことですが、食べ物を粗末にしたり、命の尊厳を軽んじたりする人です。
お稲荷さんの「稲」は、すなわち「お米」です。お米は、日本人にとって単なる食料ではなく、「命の根源」であり、神聖なものでした。
食べ物を平気で残したり、捨てたりする行為は、お稲荷さんが司る「命そのもの」を踏みにじる行為にほかなりません。 「いただきます」「ごちそうさま」という言葉には、食材となった動植物の「命」と、それを作ってくれた人への「感謝」が込められています。 それを粗末にするということは、自分を生かしてくれている全ての恵みに対して、無頓着であることの表れです。
食べ方と心の状態の深い繋がり
あなたは今、何を思いながら食事をしていますか? 「ながらスマホ」で味もわからずにかきこんだり、仕事の不満を考えながらイライラして食べていませんか?
「マインドフルネス・イーティング」という言葉があるように、食べ方にはその人の「今、ここ」に対する意識が表れます。 将来への不安で頭がいっぱいの女性が、パソコンでメールをチェックしながら、コンビニのパンを無味乾燥に口に運んでいるとします。 彼女はパンを「食べた」のではなく、ただ胃に「入れた」だけです。これでは心が満たされず、すぐにまた何かを食べたくなってしまいます。
食べ物を粗末にするとは、物理的に捨てることだけではありません。 命の恵みである食事に意識を向けず、無心で胃に詰め込む行為もまた、命を「粗末にしている」状態と言えます。 その行為は、結局のところ、「自分自身」という存在をおざなりに扱っていることの証明なのです。
「もったいない」精神が育む豊かさの感覚
「もったいない」という日本語には、深い知恵が隠されています。 これは単なる節約精神ではありません。 心理学的に、自分が持っているものに意識を向け、それを大切に使い切ろうとする姿勢は、「今ある豊かさ」に焦点を当てる訓練になります。
これは、先ほどの「足りない」という欠乏感(スカーシティ・マインドセット)の対極にある、「すでに満たされている」という豊かさの感覚(アバンダンス・マインドセット)を育てます。
例えば、冷蔵庫の余り物を見て「もう食べるものがない」と嘆くのではなく、「この人参と卵で何が作れるだろう?」と創造性を働かせる人。 これは、今ある資源を最大限に活かす豊かさの思考です。 食べ物を粗末にする人は、「どうせまた手に入る」「お金を出せば買える」という意識の表れかもしれません。 しかしそれは、豊かさの「結果」であるお金にしか焦点が合っておらず、豊かさの「源泉」である自然の恵みや人の労働への敬意が欠けています。
命を「いただく」ことの科学的・精神的な意味
天元先生は医学の道も志しており、人体の精緻な仕組みや「命」そのものについて、深い探求をされています。 先生は、「『食べる』という行為は、最もスピリチュアルで、最も科学的な行為だ」と言います。
「我々は、他の命を犠牲にしなければ生きていけない存在じゃ。野菜も、魚も、肉も、すべては『元・命』じゃ。 『いただきます』とは、『あなたの命を、私の命にさせていただきます』という、厳粛な宣言なのじゃ。 それを忘れて、ただの『モノ』として消費する時、我々は命の循環から切り離される」
さらに科学的に見ても、「腸脳相関」という言葉があるように、私たちの腸内環境は精神状態に密接に関わっています。 幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの約9割は腸で作られるのです。 命の恵みである食事を、感謝して、よく味わっていただくこと。それは、腸内環境を整え、私たちの心を科学的にも安定させる行為なのです。
お稲荷さんが司る「豊穣」とは、命が巡り、繋がり、増えていくエネルギーそのものです。 まずは、目の前の一食に宿る「命」を、心から敬い、感謝していただくこと。 それが、豊かさの循環に戻るための第一歩です。
過度な見返りを求める人(ご利益信仰)
四つ目は、「これだけお祈りしたのだから」「お賽銭をこんなに入れたのだから」と、神様との関係を「取引」だと勘違いし、過度な見返りばかりを要求する人です。
これは、特徴1の「奪う」と似ていますが、より根深い問題を抱えています。 特徴1が「足りない」という欠乏感だとしたら、こちらは「神様をコントロールしよう」とする傲慢さの表れです。
「1万円払うから、100万円ください」 これは、神様を「自分に都合よく動く自動販売機」か「高利貸し」のように見ている証拠です。
お稲荷さんに限らず、神様と人間との関係は、本来、尊敬と感謝、そして「見守っていただく」という信頼関係に基づいています。 それを「Give & Take」のビジネス契約のように持ち込むのは、非常に失礼な行為です。 あなたの親友が、「この前ランチ奢ったんだから、今度これを手伝え」と毎回言ってきたら、どんな気持ちがするでしょうか。その友情は、長続きしないでしょう。
コントロールできないことへの執着が生む無力感
心理学に「コントロールの所在(Locus of Control)」という概念があります。
- 内部統制型: 自分の人生は、自分の行動や選択によって決まる(例:「成功したのは、自分が努力したからだ」)
- 外部統制型: 自分の人生は、運や他者、環境など、外的な要因によって決まる(例:「失敗したのは、運が悪かったからだ」)
過度なご利益信仰は、この「外部統制型」の極端な表れです。 恋愛がうまくいかない女性が、「有名な縁結びの神社に何度もお参りしたのに、全く効果がない」「運命の人が現れないのは、神様が意地悪だからだ」と考えているとします。 これは、自分の人生の主導権を神様に丸投げしている状態です。
自分から出会いの場に行く、コミュニケーションの取り方を学ぶ、自分を磨くといった「内部統制的な行動」をせず、全てを運や神様のせいにしているのです。 この姿勢は、一見「信仰深い」ように見えて、実は「自分では何もする気がない」という無力感と他責の裏返しなのです。
天元先生の教え:「関心の輪」と「影響の輪」
天元先生は、私たちが何かに悩んでいる時、よく2つの円を描いて説明してくれます。
「外側の大きな円は『関心の輪』じゃ。天気、景気、他人の評価、過去の失敗、そして…お稲荷さんがご利益をくれるかどうか。これらは、お主が関心はあっても、直接コントロールできないことじゃ」
「そして、内側の小さな円。これが『影響の輪』じゃ。お主の今日の行動、発する言葉、物事の捉え方、学ぶ姿勢。これらは、お主が100%コントロールできることじゃ」
そして先生は、こう結論づけます。 「不幸な人は、外側の『関心の輪』ばかりを見て生きている。幸せな人は、内側の『影響の輪』に集中して生きている」
「ご利益をください」と神様に要求するのは、「関心の輪」にエネルギーを注ぐ行為です。 「関心の輪」は、私たちが何をしようと変わりません。結果として、無力感だけが募ります。 本当にすべきなのは、自分の「影響の輪」(=行動や努力)に全力を尽くすことなのです。
祈りとは「お願い」ではなく「宣言」
では、どう祈れば良いのか。 天元先生の教えを借りれば、祈りとは「お願い(Request)」ではなく、「宣言(Commitment)」です。
「素敵なパートナーと出会えますように」という「お願い」ではありません。 「私は、自分自身を心から大切にし、相手のことも深く尊重できる、笑顔の絶えない関係を築くにふさわしい人間になります。そのためにまず、どんな時も自分から笑顔で挨拶することを実践します。どうか、私のこの決意と行動が、良きご縁に繋がりますよう、お見守りください」
これが「宣言」です。 心理学的に、自分の目標を公に「宣言」すると、「一貫性の原理」が働き、その目標を達成しようとする実行力が高まります。 神様に宣言することは、自分自身の最も深い部分に「私は本気だ」と誓う、強力な自己暗示(アファメーション)にもなるのです。 お稲荷さんは、「ご利益をくれ」と要求する人より、「私はこう生きる」と宣言し、行動する人を、喜んで後押ししてくださるはずです。
不平不満や他責を口にする人
最後の五つ目は、常に不平不満を言い、物事がうまくいかないのを他人や環境のせいにする(他責)人です。
お稲荷さんは「稲が成る」、つまり「生成発展」のエネルギーの象徴です。 活気、成長、繁栄、プラスのエネルギーです。
一方で、不平不満や愚痴、他責の言葉は、その対極にある「停滞」や「衰退」のエネルギーです。 日本には古来、「言霊(ことだま)」という思想があります。 言葉には力があり、発した言葉通りの現実を引き寄せると考えられてきました。
不満や他責の言葉は、自ら「私はうまくいきません」「私は成長しません」と宣言しているようなものです。 豊かに実る稲穂の前で、「この土地はダメだ」「太陽が悪い」と文句ばかり言っている農夫を、お稲荷さんが応援したいと思うでしょうか。
脳は「主語」を理解できないという罠
これは、脳科学や心理学でよく言われることです。 あなたが、職場の同僚のミスに対して「あの人は本当に仕事ができない」と愚痴をこぼしたとします。 あなたの脳(特に潜在意識)は、「あの人は」という主語をうまく認識できず、「仕事ができない」というネガティブな言葉だけを強くインプットしてしまいます。
つまり、他者への不満や悪口は、そのまま自分自身への「呪い」として蓄積されていくのです。 「最悪だ」「ついてない」「どうせ無理」 これらの言葉を口癖にしている人は、自分の脳に「私は最悪で、ついてなくて、何をやっても無理な人間だ」と毎日言い聞かせているのと同じです。 このようなネガティブな自己暗示が定着した脳の状態で、お稲荷さんが司る「繁栄」のエネルギーと共鳴することは、物理的に不可能です。
不満の裏にある「自分は無力だ」という心の叫び
不平不満や他責は、先ほど(特徴4)の「外部統制型」の典型的な症状です。 「上司が悪いから、私の仕事がうまくいかない」 「景気が悪いから、店が繁盛しない」 「親の育て方が悪かったから、私の自己肯定感が低い」
これらはすべて、「自分には状況を変える力がない」という「学習性無力感」に陥っているサインです。 例えば、何を提案しても上司に頭ごなしに否定され続けてきた人は、次第に「何を言っても無駄だ」と感じるようになり、やがて会議で一切発言しなくなります。 たとえ上司が代わって改善のチャンスが訪れても、行動する前から諦めてしまうのです。 自分の人生のハンドルを他人に明け渡し、自分は助手席で文句を言っているだけなのです。
天元先生の教え:人生を変える「解釈力」
では、困難に直面した時、どうすればいいのか。 天元先生は、「事実は一つ、解釈は無数」と教えてくれます。 これは、心理療法の「認知行動療法(CBT)」の核となる考え方でもあります。
先生は言います。 「我々を苦しめるのは、『起きた出来事(事実)』そのものではない。その出来事を『どう解釈したか』が、我々を苦しめるのじゃ」
例えば、「仕事で大きな失敗をした」という事実。 Aさんは、「自分はなんてダメなんだ。もうこの会社にはいられない」と解釈し、上司や環境への不満を募らせます。 Bさんは、「なぜこの失敗が起きたのだろう? システムの問題か、自分の知識不足か? この経験から学べることは何か? 次にどう活かしよう?」と解釈します。
お稲荷さんが応援するのは、どちらの人間でしょうか。 言うまでもありません。Bさんです。
天元先生の教えは、どんな逆境(事実)の中にも、必ず「学び」と「成長の種」(解釈)を見出そうとする「解釈力」を鍛えることです。 不満を口にするのは、この「解釈」を放棄した状態です。 お稲荷さんが司る「豊穣」とは、まさに、困難という土壌からでさえ「学び」という実りを見つけ出す、その力強い「解釈力」そのものなのです。
根底にあるのは「自己肯定感の低さ」という名の器の穴
ここまで5つの特徴を見てきましたが、実はこれらすべては、ある一つの共通した問題に行き着きます。 それは「自己肯定感の低さ」です。
「奪う」のは、自分には価値がないから、外から何かを得ないと満たされないと信じているから。 「行動しない」のは、自分にはどうせできないと、自分の可能性を信じられないから。 「自分を粗末にする」のは、文字通り、自分を価値ある存在だと思えていないからです。 「神頼み」になるのは、自分の力では人生を良くできないと、無力感に苛まれているから。 そして「他責」にするのは、自分の非を認めるのが怖いから。それは自分の無価値さを証明してしまうように感じるからです。
豊かさを受け取る「器」に空いた穴。その正体は、多くの場合、「私なんて、どうせ…」という自己肯定感の低さなのです。 この穴が空いている限り、いくらお稲荷さんが恵みの水を注ごうとしても、ザルで水をすくうように、流れ出ていってしまいます。
まとめ:お稲荷さんに好かれるとは、「自分を生きる」と決めること
これまで見てきた5つの特徴は、突き詰めれば「自分の人生の主導権を放棄している」という点で共通しています。
お稲荷さんに好かれる在り方とは、その逆です。 今ある恵みに能動的に気づいて感謝し、結果を恐れず能動的に「小さな一歩」を踏み出す。 命を「いただく」と能動的に意識して大切にし、自分の行動を能動的に宣言して、結果は天に任せる。 そして、起きた出来事を、能動的に「学び」として解釈する。
つまり、「お稲荷さんに好かれる」とは、「自分の人生のハンドルを、他人や環境や神様に明け渡すのではなく、自分自身でしっかりと握り、運転していく」と決意することなのです。
この記事を読んで、「あ、自分にも当てはまるかもしれない」とドキッとした方もいるかもしれません。 でも、落ち込む必要は全くありません。 気づけたこと、それ自体が、あなたの人生が好転し始める、何よりの証拠です。
かつての私がそうであったように、人は誰でも迷い、不安になり、過去に執着し、自分を信じられなくなる時があります。 今日お話しした5つを、明日からすべて完璧にこなす必要はありません。
まずは、目の前の食事を、少しだけ丁寧に味わってみる。 寝る前に、今日あった「3つの良かったこと」を書き出してみる。 そんな「小さな実践」からで、十分なのです。
もし、一人で歩むのが不安なら
私、南極老人も、天元先生に出会うまでは、まさに今日お話しした5つの特徴すべてを抱えたまま、暗闇の中で一人、もがいていました。 「奪う」ことばかり考え、行動が伴わず、自分を粗末にし、他責を繰り返す。そんな救いようのない日々でした。
先生との出会いは、そんな私の人生の「解釈」を180度変えてくれました。 先生が教えてくれたのは、断片的なスピリチュアルやテクニックではありませんでした。
心理学、統計学、脳科学、そして古今東西の哲学。 先生は、それらの膨大な知識を、なぜそうなるのかという「本質」や「原理原則」から解き明かし、「どうすれば、再現性を持って幸福に生きられるか」という実践的な知恵として、私に授けてくれました。
今日のお話で、「なぜ」を深く掘り下げること、物事の本質を掴むこと、そしてそれを「小さな実践」に繋げることに、少しでも心が動いたなら。 もし、あなたが今、人生の迷いや不安の中で、「自分の人生のハンドルを取り戻したい」と本気で願っているのなら。
天元先生は、そうした「学び」と「実践」を望む人々が集う、オンラインのコミュニティや教材を用意されています。 これは、「入れば救われる」といった類のものではありません。 そこは、あなたの人生をあなた自身で運転していくための「教習所」であり、同じ志を持つ仲間たちと励まし合う「道場」のような場所です。
一人で暗闇を歩き続けるのが不安なら、私たちと一緒に学びませんか? そこでは、天元先生という「人生の師」の深い知恵と、同じように悩み、それでも前を向こうとする温かい仲間たちが、あなたの「小さな一歩」を待っています。 科学的で、再現性があり、そして何より温かい「生きる力」を、今度はあなたが手に入れる番です。